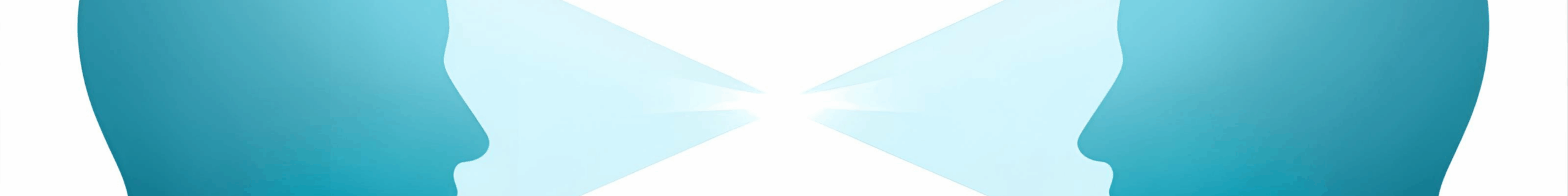組織の議論がかみ合わないとき、多くのマネージャーは「認識のズレがある」と言う。
しかし、そのズレは何がどの次元で異なっているのかを整理しなければ、永遠に原因は見つからない。
本質的にマネジメントとは、目標や方針を「揃える」ことではなく、人の見えている世界を揃えることである。
そのための基礎概念が、「視座」「視野」「視点」という三つの“認識軸”だ。
視座・視野・視点──認識の三次元構造
三者の違いを、立体的な座標で捉えるとわかりやすい。
| 概念 | 意味 | 比喩 | マネジメント上の焦点 |
|---|---|---|---|
| 視座 | どの高さから物事を見ているか。高さが上がるほど抽象度と時間軸が長くなる。 | 高所から地形を俯瞰する視点 | 目的・構造・長期的影響の理解 |
| 視野 | どの範囲までを見渡しているか。横幅が広いほど多様な関係を捉えられる。 | 地図の広がり、見えている領域の幅 | 全体最適・他部門・顧客・社会との接続 |
| 視点 | どこに焦点を当てているか。何を中心に見るかという“フォーカス”の位置。 | 望遠レンズのピント合わせ | 具体的課題・手段・打ち手の選択 |
視点は単独で存在しない。
「どの高さ(視座)から」「どの範囲(視野)を見て」「その中のどこに焦点(視点)を当てるか」という三層構造の中で初めて定義される。
したがって、議論が噛み合わないときは、この三層のどこがズレているのかを見抜く必要がある。
ズレの構造と、マネジメントが取るべき対応
| ズレの種類 | 典型的な状況 | すれ違いの構造 | 対応策 |
|---|---|---|---|
| 視座のズレ (高さの違い) | 上司は3年先の構造変化を語るが、部下は今月の施策を話している。 | 時間軸・抽象度が異なるため、同じ言葉でも指す対象が違う。 | 「いま、どの高さの話をしているのか?」を明示する。短期・中期・長期の階層で整理。 |
| 視野のズレ (範囲の違い) | 部署最適を優先し、他部署や顧客への影響を考慮していない。 | 見えている領域が異なるため、全体最適を議論できない。 | バリューチェーンやステークホルダーマップを可視化し、“全体の地図”を共有する。 |
| 視点のズレ (焦点の違い) | 同じ目的を議論しているのに、上司は「戦略」、部下は「手段」を話している。 | 見えている範囲は同じでも、焦点が異なる。 | 「この議論はいま何を深掘りしているのか」を言語化する。 |
マネジメントとは、この“ズレの次元”を正確に特定する営みである。
ズレを「誰が正しいか」で解決しようとする限り、組織は堂々巡りを続ける。
視座・視野・視点の違いが、上司と部下のすれ違いを生む
上司から見れば、メンバーは「視座が低く、視野が狭い」ように見える。
先を見通せていない、横の部署を考えていない。だから“何もわかっていない”と感じる。
一方、メンバーから見れば、上司は「現場の細部が見えていない」ように映る。
実情を知らない、机上の空論を語っている、と。
どちらも正しい。
なぜなら、見えている世界の構造が違うだけだからだ。
にもかかわらず、同じ言葉で議論することで、双方が「相手は理解していない」と結論づけてしまう。
この状態を解消する唯一の方法が、視座・視野・視点をそろえたコミュニケーションである。
視座・視野を“そろえる”だけでなく、“育てる”マネジメントへ
多くのマネージャーは、メンバーに「もっと視座を上げろ」「広い視野で考えろ」と言う。
しかし、どうすれば上がるのか・広がるのかを教える人は少ない。
これこそが、組織の学習が停滞する理由の一つである。
マネジメントの本質は、指示ではなく経験設計にある。
以下は、視座と視野を育てるための具体的アプローチである。
(1) 視座を高める──「なぜ」を共有し、想像する習慣をつくる
視座は高さであり、時間軸の長さに通じる。
視座を高めるとは、判断の背後にある構造や目的を理解することだ。
メンバーができること
- 上位層の発言や意思決定を「再現思考」する。
→「なぜその判断をしたのか」「どんな情報をもとにそう言ったのか」を推測する。 - “Why”を三段階で問い直す
なぜそれをやるのか → それが実現すると何が変わるのか → その変化は誰にとって意味があるのか。
マネージャーができること
- 指示の際に背景と意図を必ずセットで伝える。
- メンバーが「なぜ?」を安心して聞ける環境をつくる。
- 自身の意思決定プロセスを共有し、“思考のログ”を残す。
視座は教えられるものではなく、「なぜ」を共有される体験によって育つ。
(2) 視野を広げる──構造と接点を見せる
視野は横の広がりであり、関係性の理解度に直結する。
メンバーができること
- 自分の仕事がどこにつながっているかを地図化する。
(顧客ジャーニーやプロセスマップを自分で描いてみる) - 他部署の発言を“観察”する。
「なぜその論点を持っているのか」を推測する。 - 異業種の成功・失敗事例を自領域に翻訳して考える。
マネージャーができること
- 組織全体の関係性を示す構造図を定期的に共有する。
- 部門をまたぐプロジェクトや1on1など、越境の機会を設計する。
- 自部署の最適化だけで成果を出した際も、「全体ではどうか?」と一歩先の問いを投げる。
視野は情報量ではなく、接続数によって広がる。
したがって、マネージャーは“人と世界の接点を増やす設計者”であるべきだ。
視点は「選択の技術」である
視点は焦点の位置であり、最終的な選択の技術である。
視座が高まり、視野が広がるほど、正しく焦点を当てられる。
したがって、視点のズレは多くの場合、上位構造──すなわち視座や視野のズレの副作用として現れる。
マネージャーは議論の冒頭で「この話はどの高さ・どの範囲で・どこに焦点を当てているのか」を明確にするだけで、
チームの生産性を一段階引き上げることができる。
認識を揃えることが、マネジメントの最も静かなリーダーシップ
視座・視野・視点が揃うとき、組織はようやく同じ地図を見ながら前に進む。
ズレたままの議論は、いくら会議を重ねても「合意した気になっているだけ」で終わる。
マネジメントとは、人を動かすことではなく、見ている世界を揃えること。
そして、それぞれのメンバーがより高く・広く・正確に世界を見られるように、
その“認識の成長”をデザインすることこそが、リーダーシップの静かな本質である。