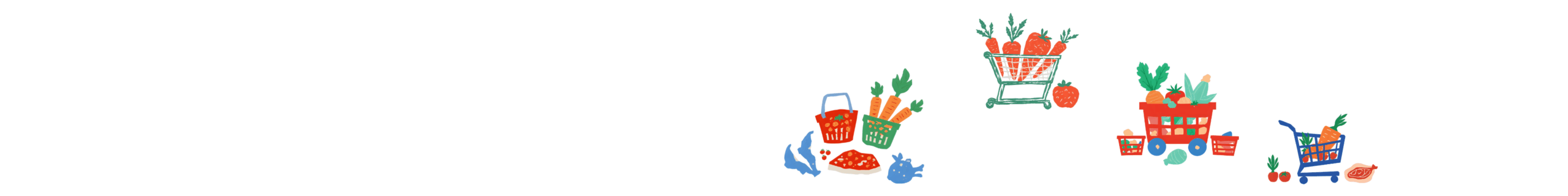「最近、ロピアより生鮮市場TOP行くようになったんだよね。安いし、なんか楽しいの。」

──会社の主婦の何気ない一言が、思いの外、いまの食品スーパー業界のマーケティング構造の核心をついている。
ロピア一強と思われていた“安くて新鮮なスーパー戦国時代”において、
静かに勢力を拡大しているのが、マミーマートの新業態『生鮮市場TOP!』だ。
IR資料を読み解くと、これは単なる価格競争ではない。
粗利を意図的に下げてでも構造を変える、スーパー業界の戦略的マーケティングの実践例である。
成熟市場でも「戦略が業績を変える」ことを証明した、
食品スーパーのマーケティング事例として注目したい。
「ロピアより生鮮市場」が起きているワケ:消費者の“価格疲れ”

ロピアの成功要因は、
「安さ×ボリューム×エンタメ性」だった。
だが、体験の新鮮さはいつか飽和する。
巨大パック、混雑、強いBGM──非日常の買い物は楽しいが、毎日は疲れる。
消費者の“疲れ”が、じわりと始まっていた。
一方の生鮮市場TOP!は、
日常の延長にある“ちょうどいい安さ”で勝負している。
「派手さ」ではなく「安心感」。
「一発の驚き」ではなく「日々の満足」。

マーケティングの観点で言えば、生鮮市場TOP!は体験の重さを取り除いた“ライト型ロピア”。
それがいま、生活者の心理にフィットしている。
生鮮市場TOP!の戦略:粗利を落として“回転で勝つ”
マミーマートのIR資料では、TOPの戦略が明確に示されている。
既存のマミーマート店舗を順次「生鮮市場TOP」へ転換し、粗利率を下げてでも売上高回転率で勝負する。
- 従来スーパーの粗利30%前後から、
- 20%台前半に落としてでもシェアを取る。
常識的に考えれば、危険な橋だ。
だがTOPは、「安く売っても儲かる構造」を同時に設計している。
つまり、“安さ”を戦略ではなく、構造の帰結として作り上げている。
覚悟の裏側にある“段階的検証”
だが、この「粗利を落としてでも勝負する」という覚悟は、感情的な“賭け”ではない。
むしろ、マミーマートは小さく検証し、確信を持って拡張するタイプの企業だ。
生鮮市場TOPの立ち上げも、最初はわずか数店舗から始まっている。
旧マミーマートを一部だけ改装し、TOPフォーマットを試験的に導入。
売上構成や客単価、購買頻度などを細かく観測し、
「このフォーマットなら回る」と確信を持った段階で、
既存店舗の大規模転換に踏み切った。
つまり、彼らの“覚悟”の正体は、検証でリスクを限定した上での確信だ。
いきなり全店転換するような賭け方ではなく、
PoC(概念実証)やMVP(最小実行可能モデル)のように、
実業の世界で“小さく試して確かめる”手法を踏んでいる。
この段階的な展開があったからこそ、「粗利を下げる」という大胆な判断も、経営上の理性を保ったまま実行できた。
言い換えれば、生鮮市場TOPは“馬鹿になれるほど慎重だった”企業だ。
この姿勢は、Webスタートアップの文脈で語られる
リーンスタートアップや検証型事業開発の考え方を、リアル店舗の世界に持ち込んだ好例でもある。
──覚悟とは、衝動ではなく構造化された決意。
それを体現しているのが、TOPの拡張戦略なのだ。
薄利を支える「多売オペレーション」の設計
生鮮市場TOP!が強いのは、“薄利多売”をスローガンで終わらせないことだ。
その裏にあるのは、「多売を成立させる仕組み」の緻密なデザインである。
- EDLP(Every Day Low Price)を徹底
価格訴求を恒常運転化し、客の信頼を蓄積。 - 日用品を削って食品尺数を最大化
「食に全振り」で鮮度ゾーンの密度を上げる。 - 味付肉・惣菜など“来店動機MD”を強化
味付焼肉カテゴリは前年同期比223.4%成長。
食品スーパー マーケティングの文脈でも注目される成果だ。
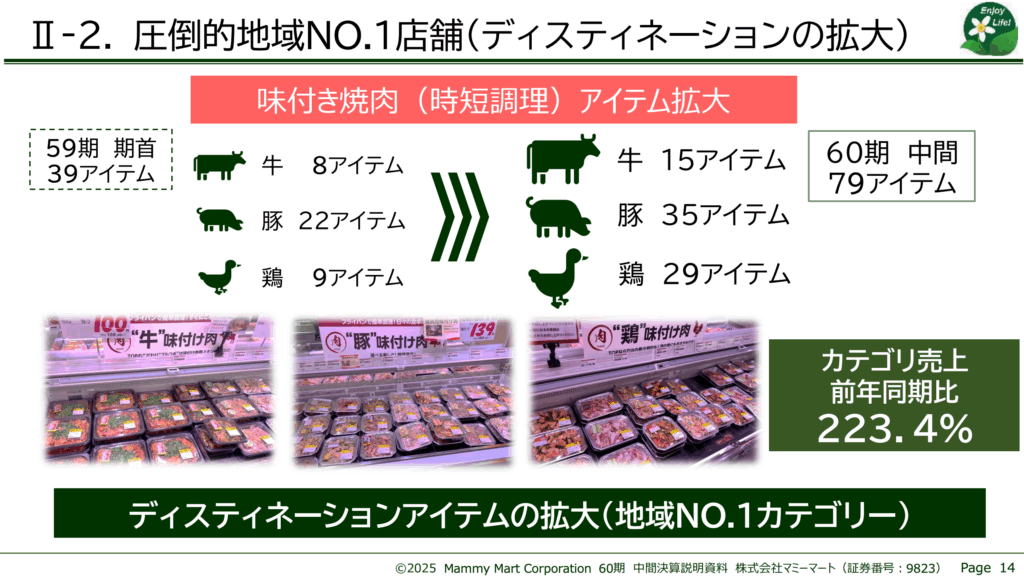
- 惣菜・弁当は受賞×PRでブランド化
「お弁当・お惣菜大賞」12年連続受賞/全10部門制覇。
売場そのものがマーケティング媒体として機能。 - 旗艦店が全国表彰(ストア・オブ・ザ・イヤー2位)
成功店舗で勝ち筋を可視化→改装・出店で横展開。 - 製販一体(彩裕フーズ)でスピード×品質両立
内製化によって“差別化×コスト最適化”を両立。 - 既存店改装で展開スピードを最大化
新規出店より低コストで効率的に展開。
──これらは単なる“節約策”ではない。
生鮮市場TOP!は、オペレーションそのものをマーケティングに転換したスーパーである。
STPで見る生鮮市場TOP!の勝ち筋:ロピア疲れの受け皿
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Segmentation | 高頻度来店層(週2〜3回の家庭購買者) |
| Targeting | 「安さは求めるが、ロピアは少し疲れる」層 |
| Positioning | “近所で気楽に行けて、確実に得した気分になるスーパー” |
生鮮市場TOP!は「価格インパクト」ではなく「生活リズム」に寄り添った。
イベント的な“お買い得体験”ではなく、習慣化される安心感で勝負している。
これは、スーパー マーケティング戦略の原点ともいえる考え方だ。
消費者の声から見えるポジショニングの違い
SNSやレビューを横断的にリサーチすると、
ロピアと生鮮市場TOP!の「買い物体験のトーン」には明確な違いがある。
ロピアは、“お祭りのような買い物”。
非日常的な「安さ×量×楽しさ」で購買をエンタメ化している。
ただし、「混雑して疲れる」「イベント的で日常使いしづらい」という声も少なくない。
一方、生鮮市場TOP!は「日常の快適さ」を中心に設計されている。
「特売日を気にせず安い」「野菜・肉・魚が新鮮で見やすい」など、
消費者は“安心して通えるスーパー”として評価している。
ロピアが“驚きの総量”を最大化するなら、
生鮮市場TOP!は“安心の頻度”を最大化する。
数字が語る構造変化
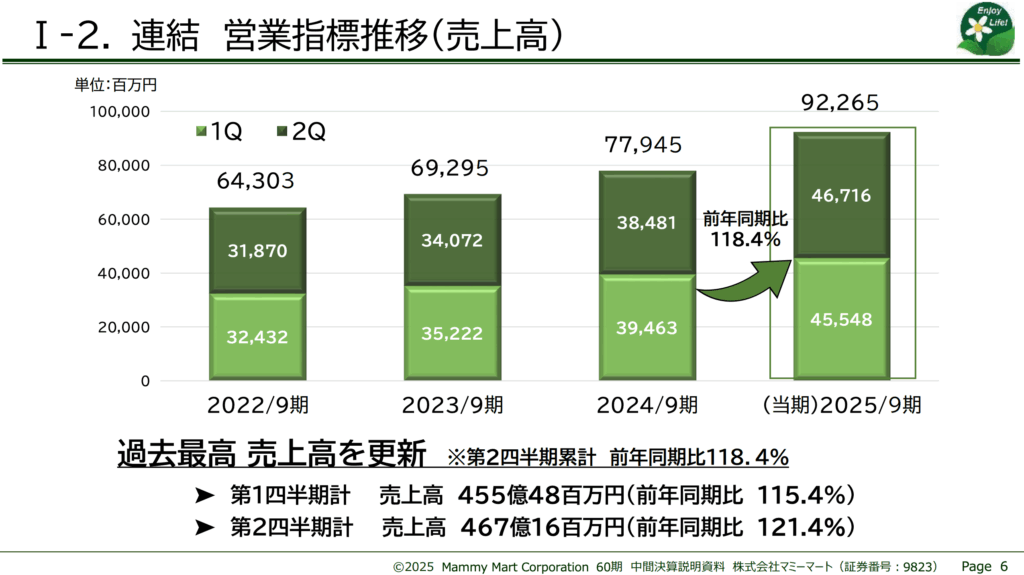
マミーマートの決算を見ると、生鮮市場TOPの転換が進むにつれ、売上構成比が拡大している。
営業利益率は大きく落とさず、むしろ効率改善で安定的な上昇を維持。
つまり、「利益率を犠牲にした成長」ではなく、“構造を入れ替えて成長した”成功例だ。
これはまさに、スーパー マーケティングが業績を動かすことを証明した事例だ。
安さを“戦略”ではなく“構造”として設計した結果である。
成熟市場でも成長できる理由
生鮮市場TOP!の事例は、
「市場が成熟しても、マーケティング戦略は成熟していない」という事実を教えてくれる。
食品スーパー業界は飽和市場と呼ばれるが、
生鮮市場TOP!は“安さ”という古い武器を、設計力と検証力で再定義した。
成熟とは、終わりではなく、最適化の始まり。
マーケティングとは、変わらない市場にもう一度“意味”を与えること。
生鮮市場TOP!はそれを最も静かに体現している。
結論:スーパー業界における戦略の再発明
生鮮市場TOP!は、古い言葉「薄利多売」を新しい意味で蘇らせた。
それは単なる価格競争ではなく、
“多売を起こす仕組み”と“覚悟を支える検証”を組み合わせたマーケティング戦略である。
派手さではなく誠実さで勝ち、スピードではなく構造で勝つ。
──それが、令和のスーパー マーケティング戦略の新しい方程式だ。
覚悟とは、衝動ではなく、構造を理解した決意のこと。
生鮮市場TOP!は、それを最も静かに証明している。